最悪だ。いつものバカみたいな元気が、どうしてこういう時に限ってなくなってしまうんだろう。
玖堂有羽はぼーっとする頭でそんなことを思った。
今日は共通の知り合いたちと来たスキー旅行の初日である。恋人である智孝に、筋肉痛を起こすまでスキーを教わろうと思っていた有羽だったが、朝からのだるさに、現地へ到着した直後にダウンしてしまった。
いち早く異変に気付いていた智孝は、「どうして倒れるまで我慢するんだ」とお小言をもらし、有羽の看病につきっきりとなった。ホテルのフロントから風邪薬をもらい、30分ほど前に服用していた。
ベッドへ横になった有羽は、肩で息をしながら智孝に話しかける。
「ごめんね、せっかくの旅行なのに……兄ちゃんだけでも楽しんできて」
智孝はふっと優しく微笑み、有羽の頭を撫でた。
「そんなこと気にするなよ」
「でも」
「じゃあ、お前が眠ったら少し滑ってくるよ。それまで何かして欲しいことあるか?」
有羽は言ってもいいものかと少しためらったが、風邪をひいてしまった不安もあり甘えることにする。
「手、つないでもいい?」
「いいよ」
そっと出された手を包み込むようにして智孝は手をつないだ。
こんな小さなことだが、有羽にとっては大きな安心となり、嬉しそうな笑顔を浮かべて目を閉じた。
それから二時間の時が流れた。
ふと目覚めた有羽は、見慣れない天井に状況を確認すべく、顔を右に動かした。
そういえば、楽しみにしていた旅行だったのに、倒れちゃったんだっけ。ふうっと一つため息をついて、体を左向きに動かした。
その時に智孝の姿を見つけ、有羽ははっと上体を起こす。
(兄ちゃん、寝ちゃってる……)
スキーをしに行く気など全くないことを表すように、背もたれのある椅子を有羽の寝ているベッドの横につけ、腕を組むようにして眠っていた。
(スキーしに行ってきてもいいって言ったのに。優しいんだから)
ずっと側にいてくれたことにくすぐったい嬉しさを感じながら、有羽は智孝にコートでもかけようと掛け布団を剥ぎ、ベッドの上へ乗る。眠る前とは大分体が軽くなっていて、その回復力の早さに一人小さくガッツポーズをとる。
それも智孝のおかげだと思った有羽は、喜びも合わせて高まる気持ちを抑えられずに、キスをしようと身を乗り出す。
だが、まだ本調子ではなかったためか、ベッドの縁(へり)で体重を支えていた手が滑り、そのまま勢いよく智孝の膝の上に落ちてしまった。
「いたたた……鼻打ったぁ」
顔を押さえながら視線を上げると、今自分がどこにいるかを疑わせるような状況にしばし固まる。恐る恐る体を起こし、智孝と目が合った瞬間にぼそりと一言。
「変態」
「ちっ違うもん! 別に寝込みを襲うとしたわけじゃなくって、これはその……! あ、あれ?」
キスしようとしたことは寝込みを襲うことになるのだろうか?と疑問に思い、そのまま考えを口にする有羽に智孝はぷっと吹き出す。
「自分でわからないのかよ」
「だって……じゃ、じゃあ、あの──風邪うつしてもいい?」
「は?」
突然何を言っているのだろうかと、智孝はぽかんとする。
問いかけはただの呟きだったのか、有羽は智孝の返事を聞こうとはせずに彼の膝の上に乗り、肩に手を添えた。
それから少しの間動かなくなってしまった有羽の名を呼ぼうと、智孝が口を開きかけた瞬間、彼の唇は有羽の唇によって塞がれた。
触れたと思った時にはもう離れていたくらい短い時間だったが、確かに柔らかい感触を受けていた。
有羽は恥ずかしさから頬を赤く染め、智孝から視線を外して行動の理由を言う。
「──って、しようと思って」これが襲っちゃうことになるかわからないし、と後半は口の中でごにょごにょと呟いた。
「それはやっぱり襲ってることになるんじゃないか?」
「え、そうなの? うわ、ショック~。エロオヤジの仲間入りしちゃったよ」
「何だそれ」
あははと声を上げて笑う智孝。有羽は智孝に寄り添ったままふっと一つ息を吐いた。
「兄ちゃんてすごいんだね。自分からするのが、こんなに緊張するとは思わなかった」
「別に緊張なんかしないぞ」
「えー!? 私なんて、すごい勇気を出したんだけど」
ひょいと体を起こしてそんな抗議の声を上げる。すぐ近くに愛しき人の顔があり、有羽は先ほどの感触を思い出し、また赤くなった。
「それより熱は下がったのか?」
「うん、大分良くなったよ。もう平気みたい」
「どれ?」
智孝はこつんとおでこ同士をくっつけ、自らの体温で熱を計る。同じような温もりに有羽は同意を求め、智孝もほっと表情を緩ませた。
それにならって笑みを浮かべる有羽が離れようとした時、急に首筋に力が加わり、そのまま智孝と唇を重ねる形になった。
予想もしていなかったことに驚きはしたが、その心地よさに身を委ねる。鼓動は高なり、顔が火照(ほて)っているのがわかった。
「ちょっと顔が赤いけど、大丈夫そうだな」
見つめ合った時にそんなことを言われては、一層顔が紅潮してしまう。有羽は何か言おうとするが言葉にならずに、何度も呑み込む仕草をとった。
「されても緊張するのか?」
「え? や、何? 今のどういうこと? え、私が緊張したから? それでキス……やー! わかんなーい!」
「落ち着け。悪かった」
智孝の投げかけた質問が何を意味しているのかわからなかったが、普通ではいられないほどの恥ずかしさを感じた有羽は、両手で顔を覆いながらその思いを一気に言葉にした。
その姿に智孝は半分呆れてなだめる。
「エロオヤジの称号は、兄ちゃんに譲るね」
「お前な」
いい雰囲気になっても、恥ずかしさから冗談を言ってしまい、その先へとなかなか進展しない二人。
けれど不満といったことはお互いになかった。
それは、相手を思いやる気持ちからきているのかもしれない。
「でも、エロオヤジって嫌いじゃないよ。相手が兄ちゃんだったらね」
からかうように有羽は言い、智孝もそれに合わせるようにして答えた。
「それなら良かった」
そしてお互いにくすりと笑うと、どちらからともなく体を引き寄せキスをした。
もう一度食べたくなる蜂蜜のように、甘くてとろけるような一時。
たまには、そんな時間に浸ってみるのもいいかもしれない。

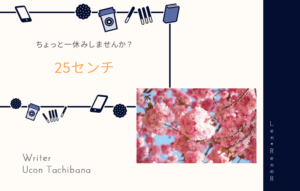







【はちみつシリーズ】
■スローペース(糖度★☆☆)
■寝起きの本音(糖度★★☆)
■甘い言葉を囁かれて(糖度★★★)