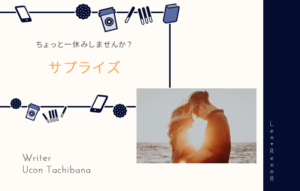「おはよ」
朝、家の前で彼は言った。私も笑顔を浮かべて挨拶を交わす。
彼の隣に立つと、自然と手を差し伸べてくれ、私はそれに応えるようにして手をつないだ。
こうして一緒に登校できるのも、今日が最後だ。
そう思うと、胸に鉛が落ちたような感覚がした。
足も思うように動かず、私は彼の手を引いて立ち止まってしまう。
「……やっぱり出来ないよ」
色んな想いが頭の中を過り、それを表現する言葉としてこんなことしか出てこなかった。
私は彼の顔を見ることも出来ずに、ただ握りしめている手に力をこめた。
「笑ってさよならなんて、私には出来ないよ!」
ふいに涙がこぼれる。
見上げた先にある彼の表情は、ぼやけて見えなかった。
耐えきれずに彼の胸へと飛び込むと、彼は強く私を抱きしめた。そして一言
「ごめん」
と囁く。
わかっているのだ。頭ではちゃんとわかってる。さよならを言えることは奇跡なんだって。
でも、どうして言えるの?
大好きな彼は、ここにこうして存在して、温もりすら感じられるのに。
本当は病院のベッドの上にいて、もうじき訪れる死を待っている人だなんて、そんなこと認められない───
「学校、さぼっちゃうか」
「え?」
「こんなに天気がいいんだしさ、何も思い出作りに授業出なくってもいいよ。な? どこ行きたい?」
「え、そんな、急に言われても……」
今までの雰囲気はどこにいったのだろう?と思わせるような明るさを振舞う彼。正直、今の状況を理解できなかった。
でも、そんな私にお構いなしで彼は一人話を続ける。
「俺、一回満天の星空ってやつが見てみたかったんだ。今から行こうよ」
「ちょ、ちょっと!」
動揺する私の手を力強く引いて、彼は駅へと走り出した。
流星に願いをのせて
「カーーーット!!」
その声と共に私たちは足を止め、周りはざわつき始めた。私たちもふっと息を吐き、お互いに微笑み合う。
「いやー、いい仕事するなぁ。やっぱり二人に頼んで正解だったよ」
にこにこと笑顔を浮かべて一人の男子生徒が歩み寄ってきた。
この人は映画研究会と称したクラブの部長兼今回の映画の監督をしている。そして、私たちのクラスメートでもあった。
「俺の場合は有羽(ゆば)に引っ張ってもらってるだけだよ」
「まあまあ、謙遜すんなって。確かに玖堂(くどう)はすごいけどな。晟(せい)だってド素人の割には迫真の演技してるさ」
「……それ、褒めてんのかよ」
「褒めてるじゃないか。でも、一番は俺の目がよかったってことだな。恋人同士の役に本物のカップルをつかうなんて、考えてもなかなかやらないし」
「結局自慢か」
「あー、僕はなんて素晴らしいんだー」
ちょっとナルシスト気味な部長に、思わず笑ってしまう私。でも、撮影と息抜きの時間をちゃんと分別して雰囲気を作るんだから、やっぱりすごい人なのかも。
「現地に着いたら、まず駅周辺のシーンを撮るからよろしくな。今日撮る分は、あと流れ星のシーンだけだ。頑張って」
「うん」
これから私たちは映画のクライマックスでもあるシーンを、三日間かけて撮影することになっている。そのために山地まで移動するのだから本格的だ。
準備が整うと、部員や配役のメンバーは次々と列車に乗り込んだ。
私は配役を与えられただけのただのクラスメートなので、旅行気分のようにわくわくしていた。持ち物だって簡単な手荷物だけだ。
私は台本だけ取り出し、棚に置こうと荷物を上げる。すると後ろからひょいと手が伸びて、荷物は軽々と棚に収まった。
「ありがと、晟」
「どういたしまして」
二人して笑うと、棚の真下である席に腰を落とす。
私が手にしている台本を見て、晟がからかうように言った。
「あれ? まだ覚えてないセリフがあったの?」
「違いますよーだ。ちょっと、最初からもう一回読んでみようと思って」
そして私は静かに第1ページ目を開いた。
この物語の内容を一言で言うと、恋人を失った女の子がどう立ち直っていくかを描いた人間ドラマだ。
彼氏である隼人(はやと)は事故に遭ってしまい、昏睡状態になっている間、いつもと変わりなく学校へ来ていた。それは彼の強い想いが生んだ奇跡。
自分がいなくなってからも彼女(リナ)が強く幸せに生きられるようにと、彼は励ましてくれるのだ。
結果から言うと、彼女は大きく成長する。彼が死んでも、前を見て生きていこうとするから。
ラストのシーンはもう撮影済みだけど、今日から撮影する旅のシーンが、この作品の要といっていいだろう。
何だか緊張する。演劇部として活動していた頃よりかも。
今日撮ると言っていた流れ星のシーンでは、彼女はこんな願い事をする。
「隼人を死なせないで下さい」と。
その願いは聞き届けられなかったわけだけど……。
「どうした?」
「うん……。隼人の願いは叶ったのに、どうしてリナはダメだったのかなぁって思って」
隼人の願いとは「リナがこれからも幸せに生きられますように」ということだ。
「うーん、やっぱりリナが願い事してる時には、隼人はもう死んでいたからだろうな」
「わー、現実的ぃ」
私はわざと無感情に言った。晟はくすりと笑って言葉をつなげる。
「でも俺としては隼人の願いが叶ってよかったな。なんか救われたって感じがしてさ。好きな人には幸せになってもらいたいもんな」
「うん。私もそう思う。本当は二人の願いが叶って欲しかったけどね。───だってヤだもん、晟がいなくなっちゃうなんて。それだけでもう、幸せじゃない」
私は晟の手をとり、きゅっと握った。
そうだよ。この温もりがなくなっちゃうなんて、絶対いや。
2
「わー! キレーイ!!」
私は満点の星空を見上げて言った。両手を広げると、自分が空に溶け込んでいくような感覚がした。
「あー、こんなことならこの前の流星群にお願いしておくんだったなぁ。これだけ星があるのにもったいない」
私は無理に笑顔を見せ、隼人にそんなことを言った。
もう叶わないことだってわかってるけど、願わずにはいられない。
この幸せを失いたくないと。
隼人は穏やかに微笑みながら、後ろから私を優しく包み込んだ。
「願いは叶うよ。見えないけど、星はいつだって流れてるから」
「本当?」
「願い事してみる?」
黙って頷く私の手に、組むようにしてつなぐ隼人。
私は目を閉じて願いをかけた。
「……何、お願いしたの?」
「言ったら叶わなくなりそうだから、教えない」
子供のように笑って隼人は言う。
「でも、絶対叶うっていう自信はあるよ」
「えー、そんなこと言われたら余計気になるじゃない」
頬を膨らませる私に、隼人は声に出して笑う。いつもと同じ光景だ。
でも隼人はふっと真剣な顔になって、私を強く抱きしめる。
「今までありがとう。すっごく楽しかった。俺、リナと会えて幸せだったよ」
「やだ……そんなお別れの言葉みたいなこと言わないでよ」
何だか嫌な予感が過り、鼓動が高鳴る。
「これから会うことも話をすることもできないけど、俺はいつまでもリナの傍にいるから。リナのこと、ずっと見守ってる」
「や、やだってば。さよならなんかしたくない!」
不安で不安でたまらなかった。その気持ちを表すかのように、涙がこぼれる。
隼人は震える私をしっかりと支え、口を開いた。
「───星になるんだ」
「え?」
「昼間の星は見えないけど、ちゃんと存在するだろ?それと同じでさ、俺も見えないけどいつでも存在してるし、リナのこと応援してるから」
何度もさよならは嫌だって言ったし、好きだとも言ったし、他になんて言えばいいのだろう?
やっとの思いで「うん」と返事をしたら、あとはもう彼にしがみついて泣くしかなかった。子供みたいに声を上げて。
私の気が済むまで彼はぎゅっと抱きしめてくれた。
ふと、目が合う。
彼はやっぱり優しい笑顔を浮かべていて、そのことに何だかほっとした私は、涙でくしゃくしゃになった顔で微笑んだ。
すると静かに彼が降りてきて……私は目を閉じた。
最後のキスは、触れた感覚もなく、切なさだけが残った。
そして次に目を開けた時には、もう彼の姿はなかった。
私は小さく「嘘つき……願い事、叶わなかったじゃない」と呟いた。
彼が傍にいることを知っていたから───
3
「お疲れ」
「あ、晟。お疲れ様」
撮りが終わって1時間が経った。自由時間となった私たちは、ついさっき演技をしていた場所へと足を運ぶ。
今も星はキラキラと輝いていた。
「はー、今日は緊張したなぁ。一回でOKもらえてよかったね」
「有羽の演技がすごくよかったから。俺も現実のような気がして、思わず有羽って呼びそうになったよ」
「えへへ。あの時は、本当に晟がいなくなっちゃう気がして……ちょっと怖かった」
その時の気持ちを思い出し、気温が下がってきたこともあって、私はぶるっと震えた。
腕をさすっていると、晟が優しく私を包み込む。ちょうど、隼人のように──
「大丈夫だよ。俺はここにいるから」
「うん……」
そう返事をしたものの、漠然と抱く不安は取り除けなかった。
私はくるりと向き合うと、存在を確かめるように晟の背中へ腕を回し、体をくっつけた。
「まだ役から抜け出せてないみたい。もうちょっと、こうしてていい?」
「もちろん、いいよ」
晟は私が安心するようにと、先程よりも強く抱きしめてくれた。
トクン、トクン。
晟の鼓動が耳に届く。それを聞いてると、段々と落ち着いてきた。
「やっぱり私はこっちの方がいいなぁ。ストーリーは綺麗にまとまってるけど、こうしてる方がうんと幸せだもん」
「そうだな。俺も一緒にいる方がずっといいや」
「ふふ、よかった」
そして再び彼の鼓動へと耳を傾ける。目を閉じると、深い安心感に包まれた。
「こうして抱きしめてもらうと、すごく落ち着くんだぁ。あったかくて気持ちよくて、安心するの」
「うん」
「ねえ、晟……私のこと、離さないでね」
「当たり前だろ?こんな幸せ、離すわけないって」
優しく頭を撫でられ、私は晟を見つめた。
微笑む彼の瞳の中に吸い込まれそう。そんなことを思っていたら、晟の顔が近づいてきた。
彼の柔らかい吐息が頬にかかり、私は慌てて下を向いた。
「イヤ?」
「イヤじゃないけど……だって、ここ外だよ?」
「うん。知ってる」
「恥ずかしいよ」
「誰も見てないよ」
晟はそう言って私の頬に触れ、唇を重ねた。
この時の私は恥ずかしいやら嬉しいやらで、少々パニック状態に陥っていた。
唇が離れてもまともに顔が見られなくて、晟に抱きつくことしかできない。
「怒った?」
「怒ってないよ。ただ」
「ただ?」
「こっ恥(ぱ)ずかしくて、顔合わせられないだけ」
「こっぱ……ぷっ、あははは」
「な、何で笑うの?」
自分ではおかしなことは言ってないと思っているので、当然の疑問だろう。
しかし晟は答えもせずに肩を揺らしてる。
「そんなに笑わなくてもいいじゃない」
「予想外な答えが返ってきたから。怒ってなくてよかったよ」
「……怒るわけないよ。嬉しいんだから」
恥ずかしくて後半は呟くように言った。そして背中を向けて一歩二歩と土を踏みしめる。
すると突然抱きすくめられ、私は声を上げた。
「じゃあ、もう一回していい?」
「星にお願いしてみる?」
からかうように答えると、晟は一瞬意表を突かれたような顔をしたが、すぐににっこりと笑って私の手をとった。
「いいよ。絶対叶うっていう自信があるから」
そして、私たちは星に願いをかけた。
END
SCENE6|ホットチョコのように。