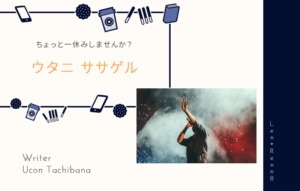「でも彩ちゃんが手伝ってくれるとは思わなかったよ。何でも言ってみるもんだね」
玖堂有羽(くどう ゆば)は会議室の扉を開けながらそう言った。
「提出するものも何とか終わったしね。それにココって入ったことなかったから」
有羽の後ろから海白彩(うみしら あや)が姿を見せる。
机の上は生徒会会議の後なので資料という紙が散らかっていた。
「あれ?」と室内を見回した有羽はホワイトボードの前で作業をしている男子生徒に声を掛ける。
「フクカイチョー、晟(せい)達は?」
呼び掛けられた彼は顔を上げると質問者を確認して
「ちょっと用事があるからって出ていったよ」
そう答えた。
ふーん、と気の無い返事を返した有羽は彩に笑顔を向けると「じゃあ彩ちゃんはこっちから紙をまとめていってくれる?」と頼んだ。
片付けを始めた二人の女性のうち、彩と呼ばれた彼女が時折じっと自分を見ていることに気がついた彼は
「何か?」
と問い掛ける。すると彼女は慌てた様子で「いえ…」と言うと、取って付けたように
「あ、あの。名前、何て読むのかしら?」
先程有羽が『副会長』と呼んでいたのを聞いていたし、資料にも名前が書かれている。ただ読み方が判らなかった。
彩がそう質問すると彼は明らかに嫌そうな表情を浮かべると
「聖。神谷聖といいます」
フルネームを口にする。
「聖──。いい名前ね」
「そうですか?……ありがとうございます」
誉める彩に心の籠もっていない礼を返すと、扉が開き男性達が入って来た。樫倉晟(かしくら せい)と遠藤遼太朗(えんどう りょうたろう)。有羽の友人だ。
彼女の視線がドアへと向けられる。タイミングの良さに聖は心の中で友人達に感謝をすると、作業に戻った。
「ただいまーって、あれ?」
見慣れぬ女生徒の姿に怪訝な表情をする二人。有羽に視線で誰だかを尋ねると、彼女はよくぞ聞いてくれましたとばかりに笑顔になると、おもむろに立ち上がりコホンと一つ咳払いをして
「ご紹介しましょう。私の大親友、海白彩ちゃんでーす」
語尾にハートマークが飛び交(か)っているような声で先輩を紹介する。
「へぇ、この人が彩先輩か。なんかイメージ通りの人だなぁ」
「うん。本当有羽の話す雰囲気まんまだよね」
二人は彩に近付くと自己紹介を始めた。
「俺は遠藤遼太朗。有羽と同じクラスで──」
そんな皆の会話を尻目に、資料の整理が終わった神谷聖は「じゃあ僕はこれで」と扉に手を掛ける。
「うん、お疲れさま」
にこやかに手を振る有羽に目を向けることなく「お疲れ様でした」と返し、退室していった。
そんな彼の後ろ姿を見送った彩は顔を曇らせて「何か悪いこと言っちゃったのかしら」と不安そうに口にする。
その言葉に顔を見合わせる後輩3人組。彼等にとって聖の行動は特別驚くことではなかったのだが、先輩はそう受け取らなかったらしい。晟が代表して弁解する。
「聖はさ、人見知りが激しいから俺らみたいに初めて会った人と打ち解けて話せないだけで、先輩を嫌っているわけではないんだ。慣れてくればちゃんと話すようになるから」
そう言われても彼女の表情は晴れなかった。
「でも…名前を聞いたら機嫌が悪くなったみたいだし」
「あー。聖くんね、自分の名前が嫌いみたいなんだよね。だから名前を聞かれるとすごく嫌そうに答えるの。だから彩ちゃんに聞かれたから、という訳じゃないと思うよ」
有羽の台詞に「ならいいけど」と少しだけ顔を綻(ほころ)ばす。
「ほい、有羽。これで全部だと思うよ」
重い空気を壊すように遼太朗が紙の束を差し出した。
それを受け取った女子生徒は
「あ、ありがとう。──うん、これで終わりだね。今日は皆様、本当にありがとうございました」
資料を確認すると笑顔でお礼を口にする。
笑いながらどういたしまして、と返す男性陣も嬉しそうだ。
「じゃあこれを置いたらみんなで一緒に帰ろ?」
有羽の提案に賛同を表わすために全員が頷いた。
チャイムが鳴り、午前中の授業が終了する。
学生達は雑談をしながらお弁当を取り出したり、校内食堂へ向かったりした。
海白彩も教室を後にして食堂へと足を向ける。いつものように有羽達とお昼を食べるためだ。
食事の載ったお盆を持ち、座る席を探していると少し離れたところに座った神谷聖が見えた。その周りには四~五人の女生徒達。彼女達は個々にお弁当や食堂のご飯を自身の前に置いていたが、彼の前だけは空間があった。
どういうことかと見ていると
「お待たせしました、聖さん」
女子生徒が食事を運んできた。受け取った人物は「ありがとう」と言って、笑顔になる。言われた彼女は嬉しそうにお辞儀をすると、グループの隅に腰を下ろした。
楽しそうな雰囲気を遠くで見ていた彩は手にしているお盆を軽く握り締める。しかし今起こした自らの行動に少しだけ肩を落とすと軽く息を吐いて手の力を抜き、グループに背を向けた。
「ああ、それは自称神谷の『親衛隊』だろ」
「しんえいたい?」
今時そんなモノが存在するのか、という口調で彩は遠藤遼太朗の言葉を繰り返す。
「ま、親衛隊って云ってもお昼の時だけ一緒にいるグループなんだけどな」
軽く笑って樫倉晟も話に加わった。
彼等の話によると『親衛隊』は昼食時のみ神谷聖と行動を共にして、登下校や授業中、休み時間などはあまり関わらないようにしているらしい。これは彼を束縛しすぎて嫌われたりしないようにと彼女達なりの配慮なのだそうだ。
そうそうと頷きながらも玖堂有羽はお弁当をつつきながら、でもねぇと漏らした。
「それでも結構聖くんは辛いみたいなんだよね。毎日のことだから気持ちは分からなくもないけど」
「でも神谷くんは嬉しそうに笑っていたみたいだけど…」
「あ、あれは摩擦を避けるための笑顔なんだって。にっこり笑ってお礼を言えば誰だって悪い気はしないでしょ?」
そうなのか、と思いながら彼等のグループに視線を送る。
しかしやっぱり彩の目には中心の男子生徒は楽しんでいるようにしか見えない。
入学してから一緒にいる有羽達と、最近知り合いになった自分とでは考えを読み取る力が違いすぎるのは仕方の無いことだろう。
そう己を慰めながらも心の中でそっと溜め息を吐いた。
そんな事がありながらも時間を見つけては玖堂有羽達のもとを訪れていた海白彩だったのだが、週に二、三度というペースが週に一度、そして二週に一度とだんだん足を運ぶ回数が減っていき、ある時からピタリと来なくなってしまった。
「最近、彩先輩来ないな」
机で頬杖をついて遼太朗がつまらなそうに口にする。
「ホント。何でだろうな」
晟がとある人物をじっと見ながらそう返した。視線の先には神谷聖がいる。
「…僕は何もしていないよ」
怪訝そうな顔をする彼に、来なくなった先輩の気持ちを知っていた遼太朗と晟は大きく息を吐き出した。
そう、彼は本当に『何も』していないのだ。
勿論挨拶をされたらする。言葉を掛けられたら返す。何かをしてもらったらお礼を言う。という当たり前のことはしていた。
でもそれだけなのだ。
自分から挨拶をしたり会話を求めたり、頼み事をすることは一切無かった。
なまじ友人である有羽や晟、遼太朗には話しかけていた事も彩にとって辛さを増す要素になっていただろう。これでは彼女が神谷に「避けられている」と思っても仕方がない。
聖の性格を知っている晟達は、決して彼が先輩を毛嫌いして避けているわけではないことは分かっていた。そしてそれを彼女に伝えてきた。
だが現に海白彩という先輩はこの場所に来なくなっている。
だからといって神谷聖を責めるわけにもいかず、二人は大きな溜め息を吐くことしか出来なかった。
そんな二人の様子を気に止めた様子もなく、聖は机に広げた資料を整理し終えると帰宅準備を始めた。
ガチャリと扉が開き有羽が顔を覗かせる。誰かを探しているのか部屋を見回すと
「ねえ、彩ちゃん見なかった?」
と聞く。首を振る友人たちを見て「そっか…」と残念そうにしている。遼太朗が理由を問うと
「彩ちゃんね、引っ越すんだって。だからその手伝いをする約束をしているんだけどさ―――」
突然、電子音によって有羽の台詞が遮られる。慌てて鞄から携帯電話を取り出す彼女の表情が明るくなった。
「彩ちゃんからだ。――もしもし彩ちゃん?うん、今は大丈夫。でさ、今日の約束なんだけど」
先輩と電話でやりとりしながら有羽は笑顔で皆に手を振ると退室していった。
残された男性陣たちの間に広がる沈黙。
「引っ越し?彩先輩が…?」
突然の情報にぼんやりする友人達の横を神谷聖が擦り抜けていく。
パタンとドアが閉まった音で我に返った晟が部屋を見渡す。聖がいないことに気づき彼が退室したことによる音源かと理解すると、机の上に紙の束が置かれたままになっているのが見えた。
聖が忘れ物をするなんて珍しいな、と思いながらそれを手にすると扉を開く。
「おい、聖!」
しかし長い廊下に呼んだ人間の姿はなかった。
「(あれ…?聖が出ていってからそんなに時間が経っていないと思ったんだけどな)」
首を傾げながら、まあいいかと室内に戻り鞄を手にすると遼太朗に声を掛けて資料を返しに行くため廊下に出た。
数日後、神谷聖は小さな公園に足を運んだ。暮れゆく中で遊具が静かに夕陽を反射している。
近所に子供がいないのか、この公園には自分一人しかいない。
ブランコに近寄ると鎖に手を掛けながら腰を下ろした。
鞄の中から細い紙包みを取り出すと視線を遠くに向ける。
作業が終わり、皆で雑談していた時のことだ。
いつもの机に座って資料に向かっている聖が辺りを見回したり、紙をひっくり返してぐるぐると円を描き始めた。
そして「誰かボールペン持っていないかな?」の声。
彼はたいして期待していなかった。晟と遼太朗はいつも「持っていない」と答えるし、普段借りる有羽はまだこの部屋に来ていない。
今回も男性陣は相変わらずの返答だった。仕方ない、と聖が教室まで戻ろうと立ち上がった時、水色のペンが差し出された。
「私ので良かったらどうぞ」
微笑んで言う彩の手元を暫(しば)し見つめる。それをどう思ったのか彼女は
「あ、これ軸は水色だけど色はちゃんと黒よ」
彼としてはただその丸みを帯びた本体を持ちにくそうだな、と思っただけに過ぎない。しかし他にペンを借りる相手もいないのでお礼を口にしてそれを受け取った。
紙の端で確かめると持ち主の言った通り黒色だ。しかも思った以上に手にしっくり来て書き味も滑らかだった。
その事に少しだけ笑みを綻(ほころ)ばす。
間近でその笑顔を目にした彩が顔を朱色に染めたが、書くことに集中していた聖が気づくことはなかった。
どのくらいの時をそうしていたのか。彩は晟の呼び掛けで我に返る。
「せんぱーい。時間、大丈夫なの?」
彼女が時計を確認すると「いけないっ!」と声を上げて勢い良く立ち上がった。
「教えてくれてありがとう。あ、そのペンはいつ返してくれても構わないから。それじゃあ」
樫倉晟、神谷聖、遠藤遼太朗と順番に声を掛けて海白彩は部屋を飛び出していった。
本当に急いでいるようで外から「こら海白!廊下を走るんじゃない!」という講師の声が中まで届いた。
「彩先輩でも慌てることがあるんだな」と残された男子達は新たな発見を笑い合った。
いつ返しても構わない。
そう言って彼女は彼にボールペンを託したが、書き終わってしまえば必要無い。忘れないよう、明日にでも返してしまおうと筆箱に仕舞った。
しかしその日を境に彼女、海白彩はいつもの部屋に姿を見せなくなった。
故(ゆえ)に聖の筆箱の中には水色のボールペンがいつまでも鎮座している。
クラスメイトで彼女と仲が良い玖堂有羽に頼んでも良かったが自分好みだったペンのメーカーを知りたかった。しかしその為だけにわざわざ彼女に会いに行く気もしない。
いつの間にかペンを返す相手が来ないことが当たり前になった。
そんなある日、先輩が引っ越すという情報が有羽からもたらされる。
海白が来ることを全く期待せずに帰宅準備をしていた神谷の手を止めるだけの力を、その言葉は持っていた。
『彩チャンネ、引ッ越スンダッテ』
携帯電話片手に出ていったクラスメイトを殆ど無意識に追いかけた。
廊下の奥まった場所で有羽を見つけた時は、ちょうど電話を切ったところだった。
聖は彼女に近寄ると、問い掛けた。
「え?彩ちゃんの住所?新しい所はまだ教えてもらっていないから分からないよ?」
「いいんだ、昔のほうで。先輩に借りたままの物を送り返すだけだから。住所変更届けを出しているだろうからちゃんと届くと思うし」
ふーん、と腑に落ちない表情の有羽だったが問い詰めても目の前の男性は答えない事を知っていたので、メモ帳に海白彩の旧住所を書くと「はい」と渡す。
「ありがとう」
その紙を受け取ると神谷聖はお礼を言い、有羽に背を向けた。
キィ…キィ…。
足を地面から離さずにブランコを揺らしていると、自分の名前が呼ばれた気がした。
顔を上げると視線の先には引っ越したはずの彼女いた。
その光景が信じられなくて「せんぱい…」と口の中だけで呟く。
「どうしたの?こんなところで」
駅からだいぶ離れたところにある住宅街の中の小さな公園、しかも最寄り駅ですら違う場所に住む人物がいれば誰だって驚くだろう。
海白彩は後輩に近付きながら問い掛ける。「あ…いえ」と少し困ったように口の中だけで返事をする神谷の手に紙包みがあるのに気がついた彼女は足を止めた。
彼は誰かを待っている──手にしている包みを渡すために。自分が来たことで困った表情を浮かべるところを見ると相手は女性かもしれない。それに、こんな所までわざわざ来るくらいだ、余程大切な人なのだろう。
邪魔をするわけにはいかない。彼にとって自分はただの先輩なのだから。
彩は、そう己に言い聞かせると笑顔を無理矢理張りつけて
「あ…っと。ごめんなさい。私、急ぎの用事の途中だったわ。すぐ帰らなきゃ。…ごめんね、声掛けちゃって」
手を合わせ軽く頭を下げ、さようならと告げてくるりと背を向け歩き出した。
別れの挨拶に聖は思わず声を上げる。「待って、先輩!」と。
サヨウナラという5文字は永遠の離別を表わしているように聞こえ、慌てて引き留めた。この機会を逃してしまったらもう二度と逢えないような気がする。
だが彼女を呼び止めたことを一番驚いたのは他ならぬ自分自身だった。
海白彩はただの先輩のはずだ。それなのに想いが声となって溢れ出てしまった。
切迫した声だったようで、足を止めた女性が怪訝な顔で振り返る。
聖は自分でも良く解からない心の衝動を持て余しながら、呼び止めてしまった彼女への言葉を探す。視線を下げると紙包みが目に入った。
ブランコから立ち上がり、彩の側へ歩み寄る。
「これ、借りていたボールペンです。今までありがとうございました」
差し出すと彼女は驚いた表情で受け取る。開くと中からは確かに水色の筆記用具が出て来た。
「これのためにわざわざ来たの?…ってことは無いわよね」
くすっと自分の言葉に呆れたように笑うと
「明日学校で返してくれれば良かったのに。でも、ありがとう」
今度は温かな微笑みを浮かべて男性に礼を述べる。
その笑顔に聖は一つのことを思い出した。
海白彩は自分と話す時はいつも柔らかい笑みを浮かべていたと。自分はその表情をどこかで心地良く感じていたということを。
そんな僅(わず)かな気付きに気を取られ、大切なことを聞き逃すところだった。
『あした、がっこうでかえしてくれればよかったのに』
「先輩…。引っ越しはされたんですよ、ね?」
「ええ」
一言で肯定をする。
「学校に何か用事でも?」
神谷聖のその問い掛けに、えっ?と首を傾げる。それから何かに気が付いたように笑い出した。
「やだ、引っ越したっていっても駅で二つ分遠くになっただけだから、別に学校が変わるわけじゃないわよ」
「えっ…そうなんですか?」
引っ越しイコール遠くの場所へ行く、というイメージがあった聖には近くに引っ越すということに考えが及ばなかった。
くすくす笑う先輩を何故だか安心したように見守る。
不思議な感覚。
それを追求する前に目の前の女性が聞いてきた。
「神谷くんはこれから何か用事でもあるの?」
首を振る男性に「そう。それじゃあ駅まで送っても良いかしら?」。
突然の申し出に少し驚いた。しかし拒む理由はない。聖は笑顔になると頷いた。
「はい。お願いします。――あ、でも先輩は急用があったんじゃないのですか?」
「あ、あれね。もういいの」
何がいいのか判らなかったが聖は深く詮索することはしなかった。
二人は並んで公園を後にする。
海白彩は神谷聖との距離が少し縮まったことに喜びを感じていた。
神谷聖は自分にとって海白彩という存在がどういう意味を持っているのかを考えることにした。
男性がふと思い出したように隣りの女性に問い掛ける。
「そういえば、先輩からお借りしたボールペン、どこのメーカーですか?」
END
紅く染まる空を見上げながら|桜左近