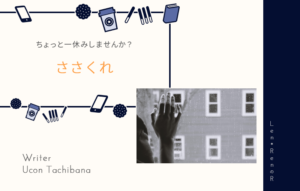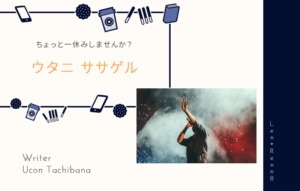あの人との距離が縮まるきっかけは、いつも雨だった。
初めての会話、初めての一緒の下校、そしてお互い名前で呼び合うようになった時も雨が降っていた。
小雨というよりは強い降り方の雨に、私は昇降口で空を見上げて息を一つ吐いた。まだ降り始めて間もないが、傘をささずに帰宅するなら制服が2倍の重さになることは間違いない。
このまましばらく待っても、本降りになっちゃうだけかなぁ。そんなことを思いながら空を見上げる。
「どう?やみそう?」
不意に後ろから声がかけられ、驚きながら振り返る。すぐ隣にその発言者はいて、私と同じような行動をとっていた。
「微妙だなー」そう言って、彼は私と視線を合わせる。
同じクラスになって二ヶ月、今まで挨拶しかしたことがなかったのに、まるで昔からの友達のような錯覚にさせられる。
「そうなんだよね、すごーく微妙」
「玖堂(くどう)も傘持ってないのか?」
「え?……あ、うん。持ってない」
返答に少し遅れたのは、彼が私の名前を知っていたからだ。まあ、同じクラスなんだから覚えていて当たり前なのかもしれないけど、今まで一度も呼ばれたことがなかったから知らないのだと思ってた。
「そっかー、俺もなんだよな」
持っていたら一体どうするつもりなのだろう?と少し疑問に思いながらも、仮定でしかならないことに考えを巡らせるのはやめ、もう一度空を見つめる。
「玖堂は家近いの?」
「歩いて15分くらいかな。だからもう走って帰ろうかなぁと思って。樫倉(かしくら)くんは?」
「俺は電車だから駅まで歩き」
「じゃあ、私と同じくらいなんだね」
「そうだな」と答えながら、樫倉晟(せい)くんはおもむろに制服を脱ぎだす。そして次に、私の前にそれを差し出していた。
「傘代わりにこれ使えよ。ないよりかはマシだと思うから」
「え、えっ?」
「じゃあ、また明日な」
動揺する私に笑顔を向けて、彼は外へ走って行ってしまった。
制服、ちょっと持っててという意味で差し出したのかと思った……自然と受け取っていた私は、その突然の心遣いをどうしようか、しばらく立ち尽くしていた。
結局、ありがたく彼の善意に授かったわけだけど、家に帰ってかなり濡れてしまったブレザーを一旦ハンガーにかけ、私は頭を悩ませた。
このまま明日返していいものなのだろうか?と。
それは意見を求めた母も同じらしく、洗濯をして返すことにした。生地は私の制服と同じはずだから問題はない。あとは明日の朝までに乾くかどうかである。
あーだこーだと試行錯誤し落ち着いた方法で、その結果は朝に二重丸を知らせた。
「何だか、余計な手間を増やしたみたいだな」と、制服を手渡す時に彼は謝った。全然そんなことないのに。
自分が濡れることよりも私を気遣ってくれたこと、そして私の部屋に男の子の物があるというだけで感じたくすぐったい高揚感、これらは私一人では味わえることではないのだ。その嬉しさは洗濯をするという手間を引いても、まだまだおつりが出るくらい。
けれど私は「そんなことないよ」という一言を彼に告げた。
なんとなくこのことがきっかけとなり、樫倉くんとはよく話すようになった。幼馴染みである遼──遠藤遼太朗(えんどう りょうたろう)くんは樫倉くんとも仲が良くて、遼を通じて親密さが増していくのに時間はかからなかった。
「晟、バスケで勝負しようぜ。負けた方が勝った方に一つパンをおごる。どう?」
「いいな。やるよ」
「あ、なんだか面白そう。私、観戦してていい?」
「応援があれば百人力」なんて冗談を口にしながら、二人は快くOKの返事をくれた。
昼休みのちょっとした時間。連日の雨に少し鬱陶しさを感じ始めていた頃、遼の提案でそれは楽しい時間に変化した。体育館を利用する生徒たちは私たちだけではないのに、彼らの本気の遊びが周囲の目を惹きつける。私の声も自然と大きくなっていった。
結局、平等に二人に声援を送ったおかげか、引き分けで勝負は終わった。
でも、バスケ部のレギュラーである遼と引き分けなんて結果はすごすぎる。素人目から見ても、遼は群を抜き出るプレイヤーだ。それなのに……。
「樫倉くんって、運動神経いいよね」
「そう?」
「うん。あの遼をあそこまで追い詰めるなんてすごいよ」
目をキラキラと輝かせて話す私とは裏腹に、樫倉くんは何か考え込むように黙って私を見つめる。「何?」と聞こうとする前に、樫倉くんの方から口を開く。
「そういえば、玖堂って遼と幼馴染みなんだっけ?」
「そうそう。ずーっと学校が一緒なの」
「それで、か」
ふむ、と樫倉くんは納得の表情を浮かべる。私はというと頭の中に疑問符をたくさん浮かべていた。
「有羽(ゆば)」
「はい」
不意に名前を呼ばれて私は少し背筋を伸ばす。
「って、呼んでもいい?」
「う、うん」
何だか鼓動が高鳴る感覚がした。変なの、ただ名前を呼ばれただけなのに……。自分の名前が特別なものになったみたい。
「俺のことも名前で呼んでよ」
「晟くん?」
「うーん、呼び捨ては?」
「晟?」
「うん。そっちの方がいいな」
樫倉くん──晟はそう言って笑顔を咲かせた。
晟は不思議な感覚にさせられる人だった。
私が遼と仲がいいのも、幼児の頃からずっと一緒だったという理由がある。兄弟みたいな感覚で、手をつなぐというような、体に触れる行動が平気でとれるのもこの時間があったからだと思う。
晟とは話すようになってからたった数ヶ月。でも、昔からの知り合いであるような錯覚にさせられるのだ。
晟の人柄もあるのかもしれない。彼はとても気さくな人で、さりげない優しさや気遣いも出来る。冗談も言うけど、その話題の豊富さには感嘆するくらいだ。
友達がヌードモデルになってと頼んだら本当にやってくれそうな感じさえある……って、いくら例えとはいえ、なんてことを考えてるんだろう私。我ながら少し呆れてしまった。
ふう、と一つ息を吐き、目の前の状況を再確認する。
降水確率50%。この確率は、その予報から傘を持って外出する人の割合と同じだということを、以前聞いたことがある。ちなみに私は傘を持って出た部類に属した。
──そして、昇降口で空の様子を窺っている彼は、おそらく傘を持ってこなかったのだろう。
「おにいさん、もしかしてお困りですか?」
からかうように声をかけると、晟は少し驚いた顔をして振り向き、私だとわかると笑顔をみせた。
「また傘持ってこなかった」
「ふふふー、私は前ので学習しましたよ。一緒に入ってく?」
傘を持ち上げ、その存在を示すと、晟は少し不思議そうな顔をして答える。
「……いいの?」
「うん!ついさっきまでは降ってなかったのにねー」
ポンッと音がして、傘は羽を広げた。立ち位置の関係もあり私は左手に傘を持ち直し晟の体を入れる──と同時にひょいと左手から重さが消えた。
「俺が持つよ」
「じゃあ、お言葉に甘えて。ありがとう」
実際、晟との身長差を考えると持ってもらう方が助かる。私じゃ万歳とはいかなくても、肩よりは上の位置で傘を持ち続けなければならなかったからだ。
それをわかっているのかいないのか、晟は私がお礼を言ったことにけらけらと笑った。
同じクラスというのは、お互いに新しい話のネタが少なくなるものの、同じネタでわかり合えるところがいいと思った。その日の授業であったことを中心に話は止まることなく盛り上がる。
「でね、あの授業の後、先生ったらポットがあるのにわざわざビーカーでお湯沸かすんだよ。それでコーヒー淹れてるんだけど怪しいよね──きゃ」
それまで笑顔で話を聞いていた晟に突然肩を引き寄せられ、私の心臓は飛び上がった。晟の温もりがシャツを通して伝わり、私は顔が熱くなるのがわかった。
え?え?え?何?
私は突然のことに足がもつれ、晟に体重を預ける形になる。
まるで時が止まったかのように感じたが、そのほんの一秒足らずのあと、自転車が私の横をすり抜けていった。
な、なんだ、自転車が来てたんだ。──って、他に理由があるわけないじゃない!何期待してるのよ!っていうか、期待って何!?
「あ、悪い」
固まっている私に気付いた晟は、ぱっと手を離し謝った。私は自分が今どんな顔をしているのかも忘れて慌てて手を振る。
「ううん!私こそ、自転車来てるの気付かなかったから……」
歩き始めた私たちは少しの間黙っていた。傘の作る空間が、なんだか恥ずかしい。
どうしよう?何か話した方がいいよね。さっきの話の続きすればいいのかな?えーと、どこまで言ったんだっけ。
けれど、そんな私の動揺も晟の言葉で打ち消されることになる。
「で、そのコーヒー普通に飲んでた?」
「う、うん!私ももらったけど、ビーカーで沸かしてるって知らなかったら美味しかったよ」
「あはは、何それ」
それから5分後、私たちは玖堂家に到着した。
「送ってくれてありがと。傘、いつでもいいからね」
私が駅まで送ったとしても、電車を降りてから自宅まで傘がないと困るだろうということで、傘を貸す代わりに晟が玄関先まで送ってくれた。
ドアの前でそんな挨拶を交わしている時、ふとあるものが目に入り、私は驚きを隠せなかった。
「晟!肩、すごい濡れてるよ!」
「……あ。あー、気にしないで」
向き合ってから気付いた彼の優しさ。晟はずっと、私が濡れないようにと気遣ってくれたんだ。
女の子用の傘に男女が一緒に入るのだったら、かなりくっつかないとどちらかが濡れてしまう。そんな当たり前のことも忘れて、私は一人はしゃいでいたことを悔やんだ。
「ね、ウチ上がっていって」
お父さんのシャツが合えばいいけど……でなければ少しでも乾かさないと。そう思って言ったことだったのだが、晟は目を丸くして言葉を失った。
私が手を引いたところで慌てて晟は口を開く。
「あ、いや、いいよ。このままで」
「風邪ひいちゃうよ?じゃあ、タオル持ってくるから待ってて!」
「ほんと、大丈夫。傘だけ貸して。な?」
「それは構わないけど……ほんとに上がっていかなくていいの?」
「ここで上がったらかっこ悪いだろ?」
「そんなこと……」
ない。と言い切れるほど、こんなシチュエーションを経験したことがないため言葉を呑み込んだ。
そういうものなのかな?私は気にしないけど、晟は気にするのかもしれない。
しばらく一人にらめっこを続けていたが、どうにも変化しそうにない晟の気持ちに見切りをつけ、私は一つため息をついた。
そんな私の気持ちを晴らすように、晟は笑顔を向ける。
「じゃ、また明日な」
笑顔を返すと、晟は駅へと歩き出した。
私はそんな晟の後ろ姿を見送り、ぽつりと呟く。
「晟は、かっこいいよ。それに──かっこ悪くてもいいもん」
そして気付いた自分の気持ち。
風邪をひいちゃうからっていうのは、もちろんあった。けれど、それよりも勝ってしまった私の願い。
もっと、一緒にいたいの。
2
「体力だけはあるから」と言ってるように、晟は風邪をひくこともなく、その後も普段通り過ごしていった。
普段通り……こんな平和な言葉に嫌気をさす日が来るなんて思ってもみなかった。
変わらない日常。私たちの関係もあれから少しも変わらない。
「有羽、今日は一緒に帰ろうね」
「うん!じゃあ、こっちの仕事終わったら彩ちゃんとこ行くね」
親友の彩ちゃん──海白彩(うみしら あや)ちゃんは中学の時からの私の先輩。優しくてかわいくて、一緒にいると楽しくて、また落ち着く人。
私はしばしの別れを告げ、生徒会室に行こうと振り返る。と、そこへ偶然晟と対面した。
「今見てたけど、ホント、彩先輩と仲いいよな」
「だって彩ちゃんのこと大好きだもん」
「あはは。なんかわかるなそれ」
チクリ。
針の先が触れたような痛みを胸の奥で感じた。
どっちの意味で言ったんだろう?私が彩ちゃんを好きだってこと?それとも──彩ちゃんを好きになる気持ちが……?
一ヶ月くらい前、晟の親友の神谷(かみや)くんと彩ちゃんが仲良く話しているのを見たのと同時に、私は彩ちゃんの気持ちを知った。
それから神谷くんと彩ちゃんがうまくいくように私に出来ることはないかな?と思って、色々と晟や本人から役立つ情報を仕入れたり、話が出来るような状況をつくったりしていた。
彩ちゃんの恋がうまくいけば……っていう下心はあった。私と晟の仲も深まるかなって思った。
でもきっとそれが悪かったんだ。純粋に応援しなかったから。
私が彩ちゃんのことを話したり、神谷くんのことを聞いたりするのと同じくらい、晟は彩ちゃんと交流をもち、興味をもった。
生徒会の仕事が一区切りついた私は、小さく声を出しながら背伸びをした。
外は雨。しとしとと朝から降り続ける雨は、窓ガラスを駆け下りる。
そんな天気もあってか、近くで自分の担当を黙々とこなしている神谷くんを見て、思わずため息が漏れた。神谷くんも晟くらい彩ちゃんに興味をもたないかな?神谷くんて、あまり深くは人と関わらないようにしてそうだしなぁ……。
重くなった気分と共に、私は机に伏せた。
純粋に彩ちゃんに会いたいという気持ちが言葉になり、神谷くんと彩ちゃんの話をした。彩ちゃんの話をしている時、私は気分が晴れる。自分でも相当な彩ちゃん好きだと思うが、楽しいことはやめられない。
しかし、このことが原因で私と神谷くんとの間に溝が出来てしまった。
彩ちゃんと知り合ったきっかけから中学時代の話になり、晟と神谷くんのことを聞いた。二人は同じ中学で、その頃から仲がいいと以前晟から聞いていたこともあり、私は叶いもしない願いを口にした。
「私たちも一緒の中学がよかったなぁ」と。
続いて、願望から生まれた一言。
「昔の晟を知っているのが神谷くんだけなんて、羨ましいな」
不意に出てしまった晟への気持ち。そしてきっぱりと言われてしまった彼の気持ち。
「今も昔も晟は変わらないよ。君に対する気持ちもね」
そうだと思う。親友である神谷くんがいうのだから、という以前になんとなく気付いていた。
きっと、私はいい友達なんだろうなって。だけど淡い期待を抱いていて……。
「つまらないヤキモチ妬かないでくれる?」
あたってた。
神谷くんの言うとおりだった。
どうしても晟に近づきたくて、どうしていいのかわからなくて。
そんな自分と神谷くんとを比べて、あまつさえヤキモチを妬くなんて。
「サイテーだ、私……」
自分の教室に戻った私は、「放課後」という独特の音色を帰宅生徒たちが奏でる中、机の上に塞ぎ込んで呟いた。
誰も気にすることはないと思ってた。誰にも聞こえないと思ってた。
だけど──あなたには届くんだね。
「どうして?」
突然降りてきた声にびっくりして、私は勢いよく顔を上げる。
声でわかっていたけど、顔を確認した途端、涙がこみ上がってくるのがわかった。胸が熱い。
どうして今なの?
会いたいけど会いたくなかった人。側にいて欲しいけど、いると切なくなってしまう人。
そんな矛盾を知られたくなくて、私は再び顔を伏せて答えた。
「神谷くんに変なこと言って怒らせちゃった……」
「聖(ひじり)に?」
意外だとばかりに晟は声を上げ、私の前の席に腰を落とす。頷く私を見て晟は何を考えたのか、少しの間のあと、質問を投げかけた。
「それ、俺に話せる?」
すごく優しい声だった。泣いてる子の頭を撫でるような、ふわふわした柔らかい感じ。
ずるいよ。いい友達でしかないなら、優しくなんてしないでよ。私ばっかり好きにさせないで。
でも、今まで蓄積されたヤキモキした気持ちはもう限界だったらしく、頭が混乱している中、私はゆっくりと言葉を吐き出していた。
「……それで、神谷くんは昔の自分のこと知られたくないって言ったのに、しつこく話を続けたから……怒っちゃった。晟は今も昔も変わらないんだから、ヤキモチ妬くなって。神谷くんが怒るのも無理ないよね。悪いことしちゃったと思って……」
全てを聞き終えた晟は、深刻過ぎず、かといってふざけるでもなく腕を組んで自分の考えを口にする。
「聖がどんな気持ちでそう言ったのかは俺の推測でしかないけど、多分、あいつには余裕がなかったんだと思う」
「余裕?」
「うん。──まあ、聖に悪いと思ってるなら、このことは気にしない方がいいよ。もし聖に何か思うところがあるなら向こうから言ってくるだろうし。何も言わないなら、この話はこれでおしまい」
「……謝らなくていいのかな?」
「大丈夫だよ。それに、有羽は悪いことしてないから」
窓の外の天気とは正反対の笑顔を見せて晟は言った。
なんとなくモヤモヤした気持ちが残っていたけど、晟が言うのならそうした方がいいと思い、私はその後もこのことについて誰にも何も言わなかった。
「聖がどんな気持ちでそう言ったのか」──晟のこの言葉が私の胸に引っかかった。
私の今までの行動が、神谷くんの気持ちを無視していたことに気付かされたからだ。
思えば、彩ちゃんの気持ちだってちゃんと聞いたわけじゃない。全部私の思い込みだ。聞けばよかったのに。せめて彩ちゃんの気持ちくらいは。
でも、今度は恐怖から彩ちゃんの気持ちを聞くことはできなかった。
もし本当は神谷くんじゃなくて、晟を好きだったとしたら?私はどう返せばいい?
私がその恐怖を抱くことになった時にも、雨は突然降り出していた──
END