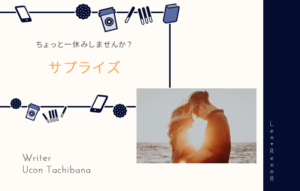文化祭も終わり、紅葉がちらほら見え始めた11月。私はお気に入りとなっている中庭に足を運んだ。休み時間や放課後にここを利用する生徒の数は、先週と比べてぐんと減っていた。すっかり肌寒くなったからなぁ……大きく息を吸った私の胸に冷たい空気が流れ込む。
それでも所属している小説部の活動のため、何か新作のいいアイディアが浮かばないものかと私は歩みを進めた。
少しいつもとは違った雰囲気を味わうために、出てきた校舎を一周してから中庭へ行こう──そう思い行動した私は、曲がり角で足を止めた。
「もっと早くに言おうと思ってたんだけど、なんか変に緊張してさ」
低く響く男性の声が聞こえた。やだ、人がいたんだ。
「どうして? 別に緊張することなんてないと思うよ」
それに答えるもう一つの声。先程の男性よりはやや柔らかいその声は、とても馴染みのあるものだった。
神谷聖(かみや ひじり)くん──私の親友と同じクラスの後輩であり、私の大好きな人だった。
盗み聞きはよくないと踵(きびす)を返そうとするが、次に出てきた親友の名前に私の足は動かなくなった。
「有羽(ゆば)は気付いてないけど、俺はわかるよ。色々、な。だからどう言い出していいかわからなかった」
「──初めからわかってたよ。玖堂(くどう)ってわかりやすいよね。僕は大丈夫。ただ、玖堂って初めてのタイプだったから、ちょっと興味があっただけだよ」
ショックだった。もしかしたらとうすうす感じていたことだけど、本人の口から聞かされるのとは受ける衝撃が全然違う。
「ちょっと興味があっただけ」──そこに神谷くんの強がりと優しさを感じた。
今度こそ私はその場を離れなきゃと思った。一歩足を踏み出せた後は、今までの苦労を疑問に感じさせる程簡単だった。足音を立てずに、というのは無理だったけど、私は体育の授業でタイムを測る並みに全力疾走した。
息を整え、私は部室に戻った。あのまま中庭に行っても考えることは同じだし、それならば気の紛れる所にいた方がいい。多分家に帰ったら否が応でも考えることになるのだから。
ガラ。
部室のドアを開けるといつもより2~3倍多い部員の数に驚いた。どうやら部員以外の人がその大半を占めているようだが、その中に親友の姿があった。
「あ、彩(あや)ちゃん、おかえりなさい」
にっこりと笑って私を出迎える彼女を見て、私も顔がほころんだ。
いくら好きな人の想い人であっても、私はこの友人が大好きだった。神谷くんが有羽を好きだからって、私は彼女を嫌いになんてなれない。私の性格もあるかもしれないけど、むしろ神谷くんが有羽を好きになるのは当然だとさえ思った。彼女は魅力的な人だから。
「今みんなと話してたんだけど、彩ちゃん明日の土曜日予定ある?」
定位置となっている自分の席に着くと、おもむろに隣に座った有羽はそんなことを言った。
私が首を傾げながらも何の予定もないことを告げると、有羽の背後に立った彼女の友人、里美(さとみ)ちゃんが呆れたように声をかける。
「有羽、理由を先に説明した方がよくない?」
「おー、それもそうだね」
軽く笑いながら謝ると、有羽はその理由を述べてきた。
今度──といっても、来年の夏にコンクールに出品する恋愛映画のシナリオを我が小説部で作ることになり、その資料収集や話し合いのために、映画部と小説部が合同で明日遊園地へ行くことなったらしい。ちなみに里美ちゃんは映画部員として参加するようだ。
「それで、私は彩ちゃんや里美のおまけで付いて行きたいなぁと思って」
「って言ってますけど、ウチの部長が有羽をヒロインに推しているので、行くのは決定です」
「いや、それは言わなくていいから。まだ決定じゃないし」
少し恥ずかしそうに有羽は里美ちゃんにツッコミを入れた。
そうなんだ……有羽がヒロインなら私も色々ストーリーが作れるかも。あれ?でも……私はその先に沸いた疑問を口にする。
「演劇部の人たちは出演しないの?」
すると二人はちょっと顔を見合わせ、有羽は困った表情を浮かべ、里美ちゃんが代弁するように答えた。
「多分出てくれると思うんですけど……まあ、難しいかもしれません。ウチの部長、来年のコンクール作品は最後だからって力入れてて、自分のイメージするヒロインは有羽しかいないって思ってるし。演劇部の、というかヒロインの座を狙っている女子が黙っていないかと」
なるほど、と思った。
確かにそれなら女子部員は出演を断るかもしれない。しかも、有羽が元演劇部とくれば、それは火を見るより明らかだった。女子の嫉妬程怖いものはないということを身を持って知っている私は大きく頷く。
有羽は明るくオープンな性格もあって、同性からのいらぬ嫉妬をもらうことが多々あった。誰にでも心を開く彼女を不思議に思い、一度聞いてみたことがある。「そんなに心を開いて、傷つくことはないのか?」と。私には到底真似できないことだった。
彼女は言う。
「傷つくこともたくさんあるけど、そうしないとわかることもわからないから」と。
もらえる優しさもたくさんあるのだと。
「それに、彩ちゃんがいてくれれば私はいつでも回復できるから。お世話になってます」
ちょっとおどけたように言ってたけど、私は彼女の気持ちがとても嬉しかった。私で何かの力になれているのなら、こんな喜びはない。
彼女は、周りの同年代の人たちよりもずっと大人だと思った。
2
「彩先輩、ちょっといい?」
樫倉(かしくら)くんはそう言って近くにあるテーブル席に私を誘った。オープンカフェのように外に用意されているテーブルと椅子。そのすぐ隣に何種類かの食べ物や飲み物を売っているお店があった。何か食べるかと聞かれ、私はミルクティーを希望する。昨日のことも、当日になって集まったメンバーにも私は緊張を隠せなかった。
土曜日当日。開園時間の15分前に現地集合となり、私はその時間の10分前に到着した。高校に入ってから引っ越しをし、有羽とは家が離れている。一緒に行くとすると一度戻るような形になるため、仕方なく私は一人向かうことにした。
メールにあと5分くらいで着くとあり、私はとりあえず見つけやすそうな入口付近に移動する。
メンバーたちが歩いてくるだろう通路に視線を移すと、私の心臓はドクンと大きく一つ波打った。
並んで歩くととても絵になるその男性二人組は、私の姿を見つけると同時に笑みを浮かばせる──来るはずのない、樫倉くんと神谷くんだった。
「おはよう彩先輩。来るの早いね」
「どうしてここに?」
私は挨拶を返すのも忘れて開口一番にそんなことを尋ねた。慌てて「おはよう」と付け足すと樫倉くんはまたニコッと笑う。この笑顔に一体何人の女性が泣くことになるんだろう?ふと沸いたくだらない疑問を捨て去り、私はちらりと神谷くんを見る。彼もまた綺麗な笑顔を浮かべていた。
綺麗という表現は男性には似つかわしくないと思うが、彼には綺麗という言葉がぴったりだった。本人は女の子顔負けの美貌に少しコンプレックスを抱いているようだけど。背の高い樫倉くんもかなり整った顔立ちをしているので、二人が揃うと異次元に来たような気分になる。
「里美に誘われてさ。面白そうだから来てみた」
有羽の気持ちを知っている里美ちゃんならやりそうなことだった。今日の予定を決めた後に彼女は自分の部へ戻って行ったから、その時に樫倉くんを誘ったのだろう。
彼が来るのはわかる。樫倉くんもまた有羽のことが好きだから。でも神谷くんが一緒に来るのには理由がみつからない。だって、昨日あんなことを話していた当事者たちなんだから。内容からして、神谷くんも親友や有羽の気持ちに気付いているみたいだし、彼の性格を考えると、誘われても「遠慮しておく」タイプだろう。
私が戸惑いの色を隠せないでいると、遠くから女性の声がした。
「彩ちゃーん! おはよー!」
有羽だった。
彼女は大きく手を振り、里美ちゃんの手を引いてこちらに駆け寄ろうとするが、私の目の前にいる男性二人が振り向いたのを見て、その足はピタリと止まった。
何やら里美ちゃんに抗議しているところを見ると、彼女も私と同様何も聞かされてなかったようだ。まあ、もし有羽が知っていたら私に何かしらの連絡はくれただろうから、知らないことは簡単に想像のつくことだけど。
少し照れた様子を見せながら今度は歩いて私たちに近づく有羽に、樫倉くんが声をかける。
「有羽、声でか」
「ここに来るの久しぶりだったし、彩ちゃん見つけたら嬉しくて、つい……でもこれなら迷子になってもすぐ見つけられそうじゃない?」
「恥ずかしいから迷子になったらアナウンスで呼んでね」
付き合いの長い里美ちゃんとの会話に皆は笑いをこぼす。いつもと変わらない光景だ。主に有羽を中心にして樫倉くんや里美ちゃんが会話に加わり、私や神谷くんは傍らで聞き役になっていた。
「あれ?なんか、有羽今日雰囲気違うね。私服だから?」
樫倉くんの言葉有有羽ははっとして、持っていたカバンを持ち上げ顔を隠す。
「あ、いや、今日は写真撮るかもしれないからメイクしておいでって言われて……やっぱり似合わないよね」
「もー! かわいいって言ってるじゃない。今日ずっとその格好で歩くの?」
「そうだよ、かわいいんだからもったいない」
「かっ……!」
有羽は驚いて、皆に見られることも忘れて腕を下げた。その顔は真っ赤に染まり、確かにいつもより大人っぽく感じた。それにしても……。
「どうして晟(せい)ってそういう恥ずかしいことをサラッと言えるの?」
私の気持ちを代弁するように有羽が言った。
「本当のことだから。有羽はかわいいよ」
「また言った!」
「あはは、耳まで赤くなってる」
「はいそこ、いちゃいちゃしない。晟はしょうがないわよ、晟なんだから」
里美ちゃんが冷ややかに二人をからかい、また三人の漫才が始まった。珍しく神谷くんもその輪に入る。
笑っている彼を見て、小さく胸が痛んだ。
神谷くん平気なの? 有羽のこと好きなんじゃないの? 里美ちゃんの言葉通り、仲のいい二人を見て苦しくならないの? どうして今日はここに来たの……?
樫倉くんも一緒だからという理由は、先程も考えたように違うと思う。じゃあ彼に誘われたから? 樫倉くんも親友の気持ちに気付いていて誘うような人じゃないだろう。だったら一体……。
私は戻ってきた樫倉くんにお礼を述べ、ミルクティーを受け取りそのまま口へ運んだ。彼はお腹がすいたと一緒に買ってきたハンバーガーを頬張った。
「あのさ、ちょっと変なこと聞くけど、昨日の放課後、先輩、東校舎の裏にいた?」
危うくむせるところだった。聞かれると思っていたけど、直球で来るとは思わなかったから。
「いや、そこに俺と聖もいたんだけど、話してたら誰かいるような物音がしてさ。見てみたらすごい勢いで走って逃げてく女子がいて。もしかしたら先輩かなー?と」
逃げたってことは知り合いの子の可能性が高いし、と彼は付け足した。
「うん……そう私、です。ごめんね」
隠すつもりもなかったし、悪気があってあそこにいたのではないけど、私は無意識の内に謝っていた。
「あはは、謝ることないって。あんなとこで話してた俺たちも俺たちだし。で、話って聞こえてた?」
これにはただ頷く。
「どこら辺まで?」
「神谷くんが有羽に興味があるって言った辺りまで……」
「あー……そっか、だからか」
樫倉くんは納得の表情を浮かべて一人頷いていた。「だから」、なんなのだろう? だから逃げたのか、ってこと?
「神谷くんは有羽のこと好きなのよね」
ためらいがちに尋ねると、樫倉くんは残っていた飲み物を一気に飲み干して微笑んだ。
「ああ、好きだったみたい」
「好きだった?」
「そ。まあ、俺が言えるのは、今日聖がここに来たのは、有羽がいるからじゃないってことかな」
「え……?」
意外なその言葉に私は呆(ほう)けたように彼を見つめる。
「それに、聖から一緒に来たいって言ったんだよ」
「……どうして?」
何だか鼓動が早まる気がした。樫倉くんの言ってることは私を期待させるようなことばかり。
「それは俺が言っちゃダメでしょ」
子供がイタズラに成功した時に見せるような笑顔を浮かべて彼は言った。
じゃあ、そんな気になることを言わないでよ。そんな気持ちが顔に出ていたのか樫倉くんは続けてこんなことも付け足した。
「朝、聖のこと見て、先輩すげー顔してたから、ヒントあげたくなった」
「!……樫倉くんてたまにイジワルよね」
「うん、ごめん」
言葉とは裏腹に樫倉くんは楽しそうな様子だった。
ズズズッと音がして、ミルクティーがなくなったことを告げると、樫倉くんはちらりと時間を確認し、私にこんなお願いを口にする。
「先輩、ちょっと買い物付き合ってよ。ご褒美に」
何に対してのご褒美よ? 私はそんなことを言いながらも彼に付き合った。
3
「わぁ、綺麗ねー」
青空が夕焼けによって綺麗なグラデーションに彩られているのを見て、私はそう感嘆の声を上げた。
遊園地の名物の一つでもある大観覧車の中から見えるその景色は地上から見るのと比べると、やはり迫力が違う。
「そうですね」
夕焼けに負けないくらい輝いた笑顔を見せて神谷くんは言った。
見惚れてしまったことにも、二人きりの空間にも私は恥ずかしさを感じ、軽く微笑んで視線をまた窓の外に向けた。
(何で神谷くん、私を誘ったのかな……)
携帯の画面を見つめている彼を盗み見て私は鼓動を早めた。
樫倉くんの買い物は“有羽が欲しがっていたアクセサリー”だった。一緒に行動していた時に有羽が私を連れてそのお店に入ったのだが、その時は買わずに出てきたのを見て、樫倉くんはプレゼントしようと決めたそうだ。
ついでに付き合ったお礼にと私も買ってもらったんだけど……本当よかったのかな?
カバンの中にプレゼントをしまおうとして、そんな考えがよぎった私は、それをじっと見つめた。
──そういえば、あの時の樫倉くんの表情にはドキッとしたな。
アクセサリー店を出る時──実際には、会計を済ませた彼にお礼を伝え、出ようと振り返った時、私たちはお店の出入口でとあるカップルを見た。
カップルに見えたのは、男性が女性を抱きとめていたから。他ならぬそのカップルとは神谷くんと有羽だった。
多分有羽が転びそうになったのを神谷くんが助けただけだと思うが、隣にいた樫倉くんは何とも険しい顔をしていた。
彼もこんな顔するんだと、普段ヘラヘラとは言わないけど、にこやかに人と接する彼を多く見てきた分、その意外性に驚いた。
私が声をかけるとハッとした彼はばつが悪そうな表情を浮かべ、
「かっこ悪いッスね、俺。でも──ダメだ」
最後に買い物に付き合ったお礼を口にして、彼はお店を出るや否や有羽の手を引いて去ってしまった。
残された私は同様の立場である神谷くんに近づく。すると、神谷くんはため息をついて「晟もまだまだですね。僕にヤキモチ妬くなんて」と私に同意を求めた。
笑ながら答えると、今度は神谷くんに誘われたのだった。樫倉くんのセリフと変わらないことにデジャヴを感じる。
「……先輩」
それで連れて来られたのがこの観覧車だった。
「海白(うみしら)先輩?」
「えっ?何?あ、ごめんなさい」
回想に没頭しすぎた。
しかし、神谷くんは気にしない様子で笑顔を見せ、携帯の画面を私に向けた。
「ありましたよ。先輩の好きなアーティスト」
「わ、本当?見ていいの?」
「どうぞ」と言って私に携帯を渡そうとするので、私は慌てて神谷くんに持っててもらえないかお願いした。
だって人のってよくわからないんだもの。怖くて簡単に触れない。
「じゃあ隣に座ってくれますか?」
……いいんですか? 隣に座って。
神谷くんは私の返事も聞かずに自分の右側にスペースをあけた。
ドキドキしながら席を移動すると、彼は私の状態に気づいてないのか、スマホを見せようとさらに近づく。微かに肩が触れ、私の鼓動は高鳴るばかりだった。
「あ、私この曲が一番好きなの」
「僕も好きです」
心臓に悪いから主語をつけて欲しい……頭の片隅でそんなことを思いながら曲を聴いていると、ふと疑問がわいた。
「そういえば、神谷くんてどんな曲を聴くの?」
それをそのまま口にすると、彼は嫌な顔一つせずに答えてくれる。その曲の動画に変えていいかと聞かれたので、もちろんと頷いた。
「最近気に入っているのは、これです」
差し出された画面の中には男性グループの姿が映し出されていた。タイトルは「ありがとうの軌跡」。歌詞も一緒に流れているので、私はそれを追いつつ歌に聞き入っていた。
『キミがいてくれて よかった
キミを好きになって よかった
今はただ ありがとうの気持ち』
歌詞に出てきた言葉に思わず息をのむ。そんな私を見て、神谷くんは口を開いた。
「失恋の歌ですけど、今の僕の気持ちをそのまま表しているようで、最初に聴いた時は驚きました──あ」
視線を外に向けた神谷くんと同じようにして私も顔を上げると、そろそろ終着を表すように地面が近づいていた。
「先輩、もう少し一緒にいていいですか? まだ肝心なこと一つも話せてないので」
こんなに早く時間が経つとは思わなかったと言われ、ほのかに胸が暖かくなる。肝心な話が気になりつつも降りる支度をしていると、神谷くんは手に持ったプレゼントを見て微かに眉をひそめた。
「それ、晟からもらったんですよね?」
「え、ええ」
「そういうことすれば玖堂が誤解するって気付かないんですかね? まあ、晟らしいといえばそうなんですけど」
観覧車から降りた私たちは遊園地の出入り口にもつながる広場に向かう。並んで歩くその距離にも私は緊張の色が隠せなかった。
「やっぱりもらわない方がよかったかな?」
「いや、先輩は悪くないです。晟がいけないんですよ。自分は玖堂へのプレゼントを買ったのに、僕にはそのチャンスを残さなかったんだから」
「え?」
「だからちょっと仕返ししようと思って、あの時すぐに玖堂を離さなかったんです。少し効き過ぎた気もしますが」
「僕も晟のこと言えませんね」と神谷くんは続ける。
笑顔で淡々と話してるけど、結構重大なことを言っているような気が……そのチャンスって、有羽に対してなの?それとも……。
動きも思考も固まった私を見て、神谷くんは小さく笑って私に向き合う。
「先輩。僕って意外と立ち直りが早いんです」
「? はい」
何のことだろうと思いつつも私は頷き、彼の言葉を待つ。
「僕が玖堂を好きだったことは知ってますか?」
「……はい」
「さっきの歌詞にもあったように、玖堂を好きになってよかったと思ってます。人を好きなるってどういうことか、教えてもらった気がして……だから、今は感謝の気持ちの方が強いです。あと、色々先輩のいい所や好きなことも教えてくれますし」
照れ笑いを含めた口調で彼は言葉をつなげる。真っ直ぐに私を見つめているだろうその顔は、逆光になってうまく見えなかった。
「今はまだ、先輩に付き合って下さいと、はっきり伝えることはできません。でも、今一番気になる人ではあります。もっと先輩のことを知りたい。僕に教えてくれますか?」
何よそれ。そんな言い方ズルイ。好きじゃないけど気になるの? ホントにもう──バカな私。
「私にも神谷くんのこと教えてくれるなら」
好きな人からそんなお願いをされたんじゃ、断る理由がない。私はそう答えて微笑んだ。
彼は「よかった」と呟き、律儀にも「よろしくお願いします」と付け足した。その仕草がなんだか可愛くて、小さく声に出して笑った。
それから私は有羽たちと合流するまで「ありがとうの軌跡」を聴かせてもらった。
私はどうやら失恋にはならないみたいだけど、この歌をあなたに捧げます。
──気にしてくれて ありがとう
END